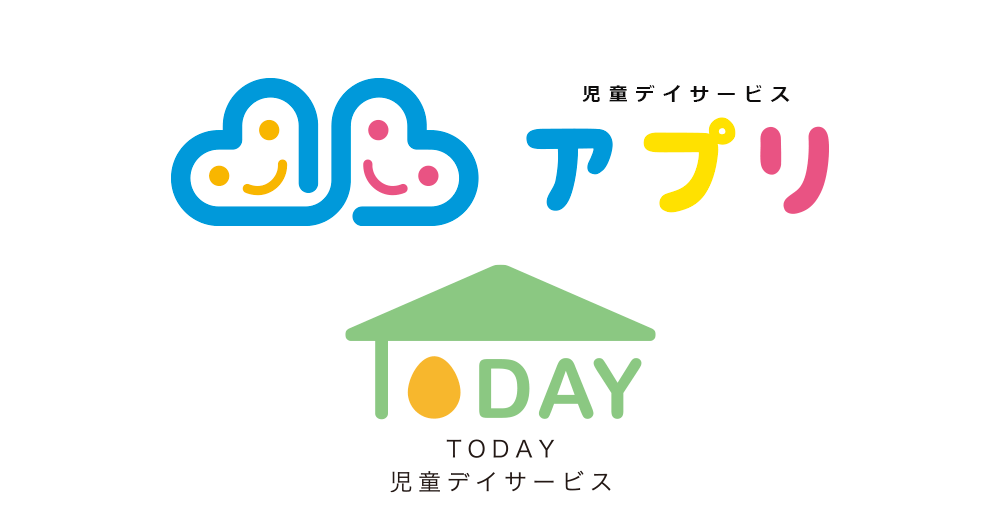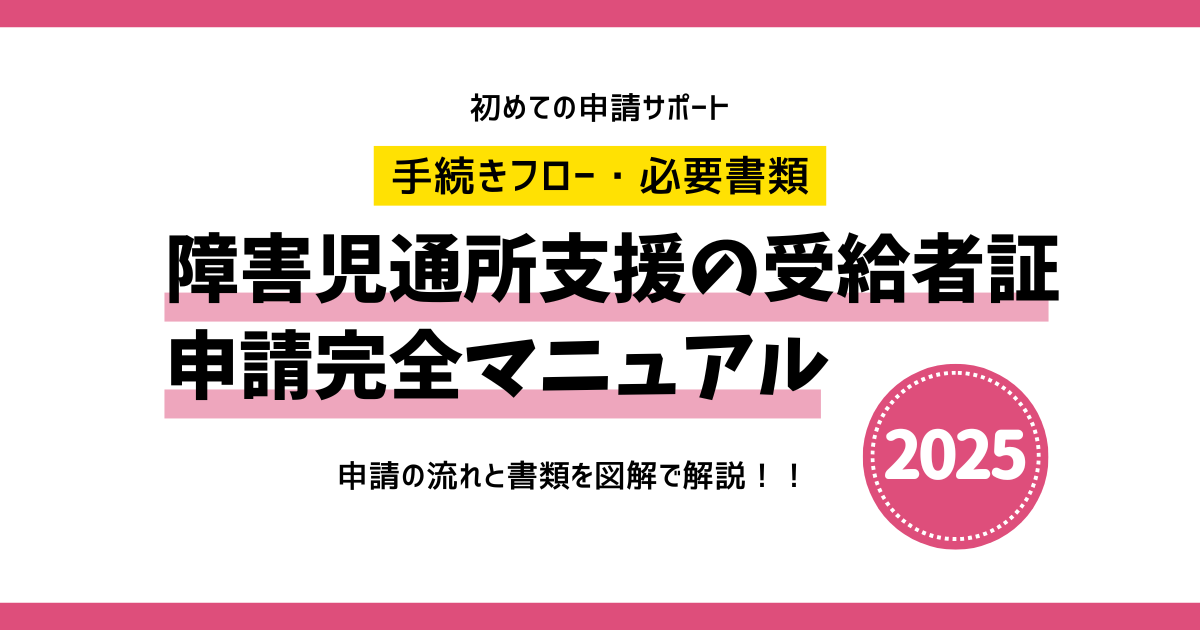こんにちは。児童発達支援・放課後等デイサービス「アプリTODAY」です。
放課後等デイサービス(放デイ)や児童発達支援を利用するには、市区町村が発行する「障害児通所支援受給者証」が必須です。本記事では2025年度制度をもとに、準備→申請→支給決定→利用開始を詳しく解説し、必要書類をチェックリスト形式でまとめました。自治体差が出やすいポイントやつまずきやすい箇所も補足しています。
受給者証とは
受給者証は利用許可証と料金区分通知書の2役を担います。
| 主な記載事項 | 内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 有効期間 | 原則1年 | 誕生月で区切る自治体も。更新申請は期限の3か月前から受付 |
| 支給量 | 月〇日・〇時間など | 平均は月10〜12日。不足時は増量申請可 |
| サービス種別 | 放デイ・児発など | 同じ証で複数サービスを併用できる |
| 世帯所得区分 | 0円/4,600円/9,300円/37,200円 | 上限額の詳細は料金ガイド記事へ |
- 制度詳細(厚労省手引き)
https://www.mhlw.go.jp/content/000822486.pdf
申請前の準備
相談支援事業所を選ぶ
受給者証取得にはサービス等利用計画案が必須です。まずは指定特定相談支援事業所で面談予約を取りましょう。
- 事業所検索はWAMネット
https://www.wam.go.jp/
選定基準
- 専門分野:医療的ケア児や重症心身障害児の実績
- レスポンス:面談から計画案提出まで1〜2週間が目安
- モニタリング体制:半年ごとに家庭・学校訪問があるか
面談・アセスメント
面談では診断名・特性、保護者就労状況、希望サービス種別や利用回数を聞き取り、サービス等利用計画案を作成します。
申請手続きフロー(5ステップ)
申請は以下の5ステップで進みます。書類提出から交付まで2〜4週間が目安です。
- 詳細
-
福祉課に申請書一式を提出
- つまずきポイント
-
所得証明・意見書の添付漏れ
- 詳細
-
相談支援専門員が家庭・学校訪問
- つまずきポイント
-
学校側の日程調整に時間がかかる
- 詳細
-
支給量を審査
- つまずきポイント
-
利用目的と支給量が合わない場合あり
- 詳細
-
有効期間・月支給量確定
- つまずきポイント
-
郵送交付だと受け取りに時間差
- 詳細
-
施設と契約→支援開始
- つまずきポイント
-
契約書のキャンセル規定を必ず確認
必要書類チェックリスト
受給者証交付申請書
- どこでもらえる?
市区町村窓口/HP - 注意ポイント
押印忘れに注意
医師意見書
- どこでもらえる?
かかりつけ医 - 注意ポイント
診断名・療育内容の記入漏れに注意
サービス等利用計画案
- どこでもらえる?
相談支援専門員 - 注意ポイント
保護者の署名忘れに注意
所得課税証明書
- どこでもらえる?
市県民税課 - 注意ポイント
最新年度のもの、世帯員数不足に注意
マイナンバー確認書類
- どこでもらえる?
ご自身でご用意ください - 注意ポイント
番号が鮮明なコピーを準備
支給決定後にやること
施設見学と利用契約
受給者証が届いたら、まずは実際に通所する候補施設を見学します。平日と長期休暇の両方で雰囲気を確認すると、職員配置や活動内容の違いがわかりミスマッチを防げます。見学後に契約書へ進む際は、次の3点を必ずチェックしてください。
- キャンセル規定:当日欠席や長期休暇の振替ルール
- 実費負担:教材費・外出費・給食費などの上限と請求タイミング
- 個別支援計画の見直し時期:多くの施設は利用開始後3か月以内に初回レビューを行います
これらを把握しておけば、「思ったより費用が高い」「短縮授業日に預かってもらえない」といったトラブルを避けられます。
モニタリングと変更申請
通所開始後は、半年ごとに相談支援専門員が家庭や学校を訪問し、サービス等利用計画のモニタリングを行います。利用目的が変わった、支給量が足りない、と感じた場合は次の手順で調整できます。
- 保護者・施設・相談支援で課題を整理し変更理由書を作成
- 追加資料(学校所見・医師意見書など)を添付
- 福祉課へ変更申請→審査→支給決定通知を受領
追加資料が具体的であるほど審査がスムーズになり、月あたりの日数増量やサービス種別追加が認められやすくなります。
よくある質問Q&A
- オンライン申請はできる?
-
一部自治体で電子申請を試行中。多くは窓口or郵送提出。
- 医療的ケア児でも取得可能?
-
可能。必要医療行為を医師意見書に明記。
- 支給量が足りない時は?
-
不服申立て・再審査請求が可能(通知3か月以内)。
- 更新申請はいつ?
-
有効期限の約3か月前から受付。意見書簡易版とモニタリング票が必要。
まとめ
受給者証は、障害児通所支援を利用するための許可証であり、同時に世帯所得別の料金区分通知でもあります。手続きは
準備→書類提出→訪問調査→審査→交付→契約
の順で進み、交付までにおおよそ2〜4週間を要します。書類の不備やキャンセル規定の見落としが失敗の原因になりやすいので、相談支援専門員と連携しながら余裕を持ったスケジュールで進めましょう。