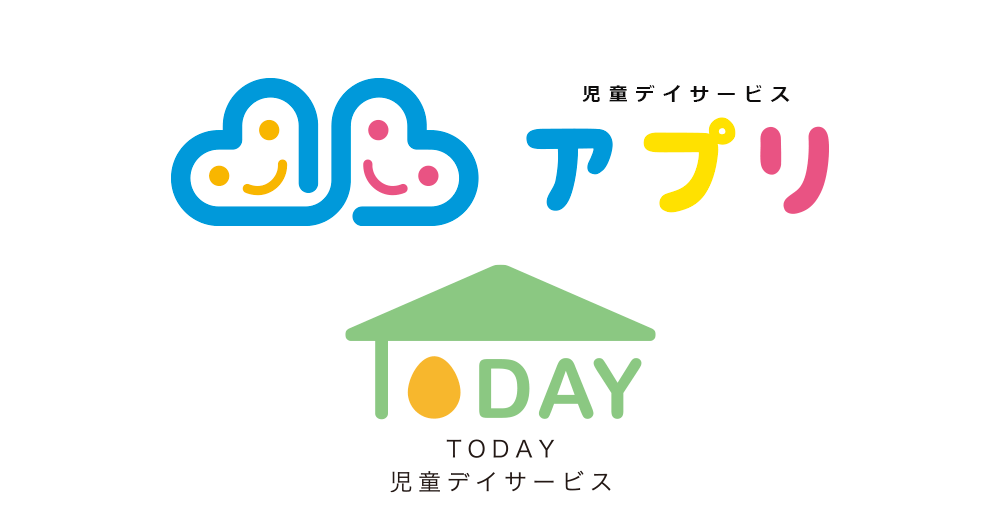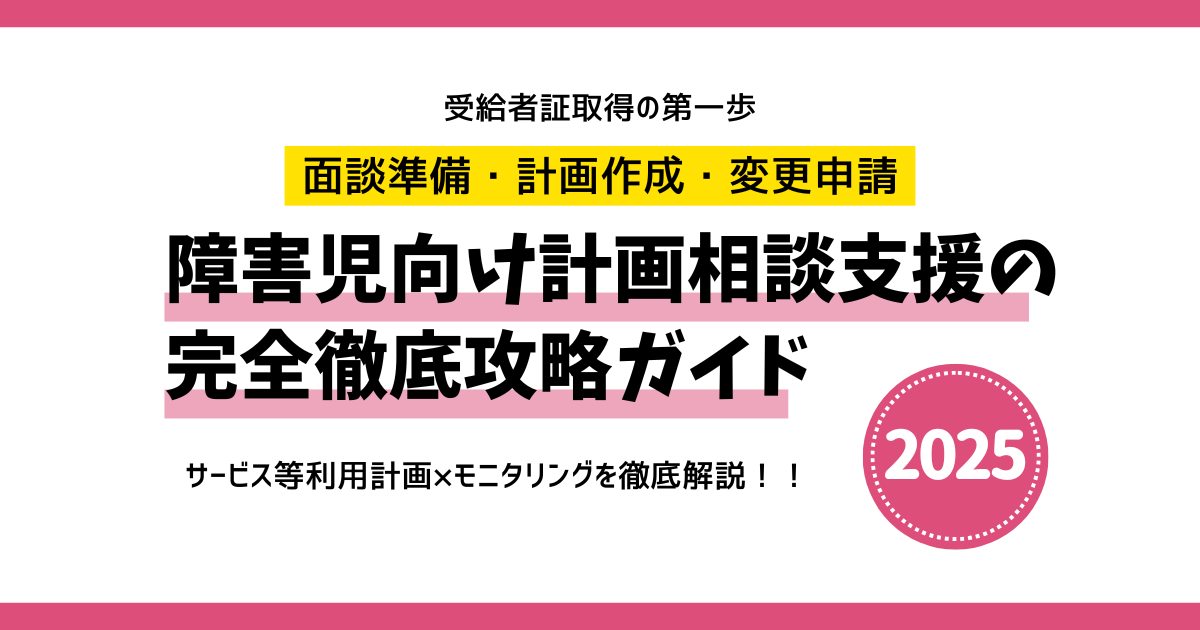こんにちは。児童発達支援・放課後等デイサービス「アプリTODAY」です。
放課後等デイサービスや児童発達支援を公費負担で利用するためには、市区町村へ提出する「サービス等利用計画」が欠かせません。計画を作り、半年ごとに見直してくれるのが計画相談支援(相談支援専門員)です。ところが「面談で何を話すの?」「モニタリングって何をするの?」と戸惑う保護者が少なくありません。
本記事では計画相談支援=“福祉サービス利用の伴走者”と位置づけ、準備から更新までをステップごとに解説します。
- 厚生労働省 「相談支援業務に関する手引き(令和6 年)」https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001335080.pdf
計画相談支援の基礎知識
計画相談支援は、障害児が地域で切れ目なく支援を受けられるよう 「計画作成」「モニタリング」「変更申請」 を一貫してサポートする制度です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的根拠 | 障害者総合支援法 第76条 |
| 対象 | 障害児通所支援(児発・放デイ等)を利用する児童 |
| 利用料 | 0円(全額公費)※一部例外あり |
| 主な役割 | ①計画作成 ②半年ごとのモニタリング ③変更申請支援 |
フルマラソンで伴走者がペース管理と給水サポートをしてくれるように、相談支援専門員はサービス利用の「ペース」と「内容」を調整し続けます。
- 厚生労働省 「障害のある人に対する相談支援について」WEBページhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/soudan_shien.html
サービス等利用計画 5ステップ ─ 時系列で見る流れ
サービス等利用計画は準備→申請→利用開始→モニタリング→変更・更新の順に進みます。各ステップで何をするのか、担当者と書類を整理すると迷いません。
家庭・学校での困りごと、医療的ケアの有無、送迎体制などをヒアリング
ヒアリング内容をもとに「目標」「サービス種別」「支給量」を可視化
計画案と受給者証交付申請書、医師意見書をセットで提出
2〜4週間で受給者証が交付。施設と契約して利用スタート
半年ごとに専門員が面談し、目標の達成度や支給量の妥当性を点検。
面談をスムーズにする準備
面談で「何から話せば…」と戸惑わないよう、次の3点を事前にメモしておきましょう。
発達検査(WISC、K式)や主治医の診断書を持参すると、専門員は強み・課題を客観的に把握できます。
学習遅れ>身辺自立>集団適応 のように並べ替えておくと、計画案に反映しやすくなります。
学校迎えの可否・兄弟同乗など、送迎体制は支給量(日数)決定の重要ファクターです。
モニタリング訪問で見る4つの視点
モニタリングは計画のPDCAサイクルで言えば “Check”。半年に1度、専門員が家庭や学校を訪問し次の4点を確認します。
| 視点 | 具体的な質問例 |
|---|---|
| ① 目標の達成度 | 「声かけで着替えができるようになった?」 |
| ② 利用状況 | 「通所回数は足りている?」 |
| ③ 家庭・学校の変化 | 「担任が替わって困りごと増えていない?」 |
| ④ 追加ニーズ | 「夏休みだけ日数を増やせる?」 |
達成度が高ければ目標をステップアップし、不足があれば支給量や事業所を見直します。
相談支援事業所を選ぶ4つの基準
専門性・スピード・連携・評価 の4視点で比較するとミスマッチを防げます。
- 専門分野:医療的ケア児や重症心身障害児の支援実績
- レスポンス:面談予約から計画提出まで1〜2週間が目安
- 連携力:学校・医療との情報共有の頻度
- 第三者評価:WAMネットの評価結果や口コミ
複数事業所を候補に挙げ、電話対応の分かりやすさや見学時の説明の丁寧さも比較すると失敗が少ないです。
よくある質問Q&A
- 相談支援専門員は変更できる?
-
可能。市区町村に「変更届」を提出すれば、別事業所へ切り替えられます。
- きょうだい同じ専門員に依頼できる?
-
可能。同じ計画相談支援事業所に依頼すると面談やモニタリングを合同で行えるため家族の負担軽減になります。
- モニタリングを欠席したら?
-
電話・オンラインで代替可能。ただし対面のほうが課題を共有しやすいため、半年に一度は対面訪問を推奨。
- 支給量を増やす手順は?
-
変更理由書+追加資料(学校所見等)を提出して変更申請します。
まとめ
計画相談支援は、障害児通所支援を「適切な量と質」で継続 するための伴走者です。面談前に診断名や家庭の送迎体制を整理し、半年ごとのモニタリングで課題を共有すれば、サービス等利用計画はお子さまの成長に合わせて進化し続けます。相談は無料ですので、遠慮なく専門員を頼りながら最適な支援環境を整えましょう。
参考・出典
- 厚生労働省 「相談支援業務に関する手引き(令和6 年)」
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001335080.pdf - 厚生労働省 「障害のある人に対する相談支援について」WEBページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/shougaishahukushi/service/soudan_shien.html